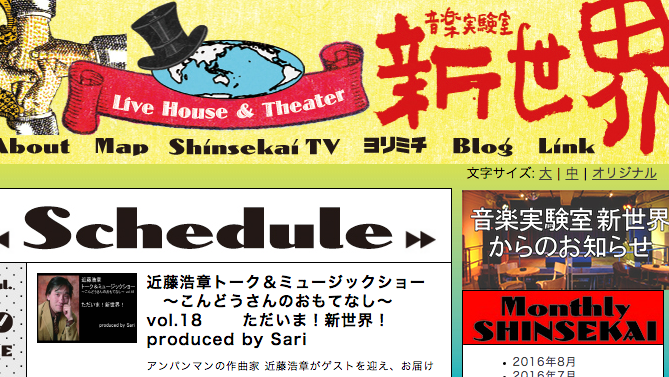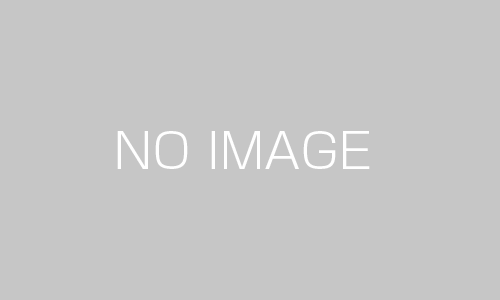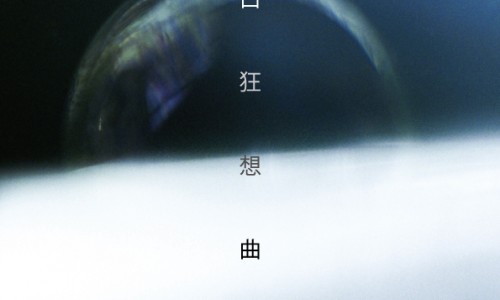演劇とそのボディ・スナッチャー、リクウズルームについて⑴/山下望
これまでのリクウズルームの演劇は、高速回転で多線・多方向に辻褄が書き換えられていく「書かれた」台詞とその戯曲のテキストを舞台上で「喋る」身体の解離が起きる、つまり始まって終わる上演時間中にリニアに収束しようとする「物語」の磁場に抵抗する運動が舞台の前面に出ているのが特徴だったのだが、作・演出の佐々木透が「だいぶわかりやすくなってきた」(2016年1月9日のこまばアゴラ劇場でのアフタートークより)と述べているように、今作の『アマルガム手帖+』では一応「X君に恋する主人公の女子高生Yが遺した手帖、から浮かび上がる人間関係のこじれ」にまつわる単線的な筋書きがあるものとして観られるようになっている。
しかし、今回もそれを一字一句覚えなきゃいけない俳優達が、西尾維新原作のナンセンスなノリツッコミ会話劇を何割か増しで複雑にしたような戯曲に翻弄される演出の醍醐味が全開だったのだが、正直どういう計算に代入されてある高校のX君とYちゃんとY’(分身)さんとZちゃんの三角関係がこじれた物語になったのかは観ているだけでは判然としなかったのだが、なおかつ理想の分身がなぜ二か国語が混じる白人女性の姿なのかも謎のままなのだが、主人公の願望を叶える分身役の青年団のブライアリー・ロング(平田オリザ原作で深田晃司監督の映画『さようなら』にも主演している)が元教師のタコ焼き屋だと推測される男に向かって全身の手振りを使って金髪を振り乱しながら文字化けしたような、助詞や接続詞が数式に変換された非線的な文節の異常な長台詞(なぜか微積分の記号の部分は外国語の発音で、一応後ろに字幕でその計算式が映る)を吃るとか訛るどころではない宇宙からのメッセージを受信するかのような不自然なリズムとイントネーションで畳み掛ける場面は思わず「どうかしてる!!」と嘆息させられてしまった。登場人物の中で実は一番計算高いのではないかという疑いのかかる、水商売まで視野に入れて将来の家計の「心配」を事細かにシミュレーションする母親(西尾佳織)が、X君に心乱されるYに言った間違いがあってはならない=できちゃった婚という伏線が件のY’の長台詞でのとち狂った論理展開(タコ焼き=セクハラ理論?)に変換される言語としては、沖島勲監督のデジタル映画(『一万年、後…。』『WHO IS THAT MAN!?』など)を連想したこの新作での変化を一言で表すと、より一筋縄ではいかなくなっている。
ここで、この作品における言語(戯曲)と身体(俳優)のせめぎ合いのメカニズムにもう一歩踏み込むために、私が観ることができた過去作、2012年のアトリエ春風舎での公演『下生しさらせ右に左に弥勒で上に』の場合を振り返ってみよう。まず主人公であろうと思しき俳優が登場して友達との対決に負けない「泥団子の作り方」を事細かに描写・解説していく冒頭の語りから、まんじゅうこわい→ライオンの脱出→みちるの試験、と場面が転がってゆき、一般的なストーリーテリングの加減を越えた量と速度でパフォーマンスされる、些細な単語間に連想のネットワークが張り巡らされて分岐・増殖していく過剰な台詞の奔流から各自の一定の解釈能力をもとに物語の断片を収束させてその都度新たな辻褄を星座を観測するようにして読み取るのは観客それぞれに任されている。
下に右に左に上に、と「物語の重力」に拮抗しようとする書かれた意志=戯曲、にコントロールされる身体を張った俳優たちの、すなわち彼らが顔形と声を与える現実の舞台上で予測不可能な方向に絶え間なくとりとめのない問答を繰り広げる6つの知性体の、有限の始まりと終わりが不可避的に必ずやって来てしまう「その時その場の実演の時間」に伴う引き裂かれ具合がやたらと面白かったのだが、時事ネタも織り込まれた言葉遊びの精度とは別に、舞台空間でそれぞれの役柄が互いに向き合ったり独り言だったり稀に会話に混じってきたりの進行の中で、それぞれの口で言っていることと体でやっていることの噛み合わなさが、浮かび上がる物語の傍らで起きている出来事の衝突が、互いの「無関係」さゆえに妙に感動的に笑える場面もあった。
どこかに『物語製造過程法』があるという主人公が付いた嘘がこの作品を動かしている基本的な設定なのだが、時事ネタやダジャレのような言葉遊び以外に文学史からの引用が目立っていたり、厳密に夢の自動生成がプログラミングされているかのようなリクウズルームの舞台は書くこと(書かれた言葉)の極限を演劇にするという企図が根底にあるのだろうか。というのが最初に観た印象である。そこで起きているのはつまり、俳優の演技を介した、いや劇場空間に組みこまれた互いにバラバラの脳と身体をまたがる、戯曲の執筆と発声練習と本番の反復する時間を挟んだ「錯乱」のマルチコア化?
その後出版された徳永京子+藤原ちからの「演劇最強論」に載っている小劇場作家リストの短評でも「相対化の鬼」と称されている通りのこの脱臼に次ぐ脱臼、反転に次ぐ反転は、『アマルガム手帖+』でも劇中で榊原毅が演じる教師や西尾佳織が演じる母親のような登場人物がその時居たはずの学校や家庭だったはずの状況設定を逸脱していく暴走するモノローグにその片鱗があるのだが(そのため先生は教職を追われることになる)、戯曲に書かれた役を演じる生身の人間が数式の記述通りに動くことができないという軋みが極致に達している。「戯曲表現たりうる限界はどこまで可能なのかを問う思考実験」(パンフレットより)である『アマルガム手帖+』は「母親が降霊術を行い、Yの友人・Zを呼び寄せるシーンで、母でありながらZであるということの説明的なト書きを戯曲上から排除し、積分式を用いて“母以上Z未満”という抽象的な状態を視覚化させて」書かれている。方程式で表された役柄を文字通りに演じる=リアルに「再現する」とは?
これは見方を変えれば、佐々木敦「即興の解体/懐胎」での複数回上演される一つの舞台作品が実現に向けて想定している「理想型」とは?の議論が手がかりになる。
『さて、ならばこのような体操選手と、ダンサーやコレオグラファー、或いは演出家や俳優は、詰まるところ同じことをしているのだろうか?そうではあるまい。もちろんスポーツと芸術は違う、というような馬鹿らしいことを言いたいわけではない。私が思うのは、満点があくまでも「満点」であるスポーツとは異なり、演劇やダンスや、或いはその他の芸術表現と総称し得るような営みは、相対的価値判断は明らかに可能であるのにもかかわらず、しかしそれを可能足らしめている筈の「理想型」と呼べるものは本当は無い、それは到達不可能であるがゆえに到達へのベクトルを牽引する無限遠点のようなものとしてさえ実は存在していない、つまりそもそもそれを想定すること自体が根本的に誤りなのではないだろうか、ということなのだ。』(佐々木敦「即興の解体/懐胎 演奏と演劇のアポリア」より)
「言葉と体が、言っていることとやっていることが食い違っているズレ」。これはいわゆる1970年代の柄谷行人が考えた、夏目漱石の小説が倫理的な位相(頭の恐ろしさ)と存在論的な位相(心臓の恐ろしさ)の二重構造に分裂しているという「意識と自然――漱石試論」から始まって『彼らはそれを意識していないが、そう行う』(『探究Ⅰ』)、そして『高い理念に導かれた純朴な人々が善意と誠意から無欠の理論を実践して、滑稽なまでに愚劣な、むごたらしい悪事を招来するのはなぜなのか』(大澤信亮による山城むつみ「ドストエフスキー」の書評)といったようにマルクスとドストエフスキーとウィトゲンシュタインを独自に咀嚼した日本の文芸批評で問われてきたモチーフでもある。
まさしくバフチンが言う「対話的に作者に敵対する複数の声=ポリフォニー」が生まれる構造を持つ、錯綜した戯曲の次の段階で、数式が物語に侵入してくる『アマルガム手帖+』に戻ると、そもそも不敵な存在感で劇中の現実の反転を支えるタカハシカナコの演じる冴えない女子高校生が数学の授業の最中に見た夢(?)に「彼」と「私」と「友人」と「母」の関係を組み替える方程式が混じってくるわけだが、その異物感は、喩えるならば「2+2=5」になる世界について延々と考えるドストエフスキーの「地下室の手記」の主人公の台詞みたいなものだろうか。
『ドストエフスキーは、この「数学」に反撥していた。「地下生活者」は、2+2=4の如き確実性に反撥し、われわれの“意識”は、いわば2+2=5を欲するのだ、という。ドストエフスキーにとって、非ユークリッド幾何のニュースは、まさに2+2=5の如き世界を示唆すると思われたのだろう。しかし、ユークリッド幾何の公理系のなかで、いわゆる平行線の公理は最初から疑わしいものとしてあったのであり、また非ユークリッド幾何も、べつの公理を選んだとき厳密に「数学的に」演繹されるものである。つまり、どちらも公理主義的であり、いわば「数学的」なのだ。が、ドストエフスキーが非ユークリッド幾何に、「ユークリッド的知性」をこえるものとして宗教的な意味づけをしたことは確かである。』(柄谷行人「探求Ⅰ」)
……およそ十数年ぶりに「探求Ⅰ」を開いたらこういう一節が飛び出してきた。柄谷行人によれば、その計算には「平行線が無限遠点で交わるような公理系」を持つ「ユークリッド的な時空間から非ユークリッド的な時空観への変容」が賭けられているとのことで、何か最近話題の思弁的実在論みたいなのだが『超越者(無限なるもの)であると同時に人間(有限なるもの)』であるキリストが出現したことによって物理的にそうなる非ユークリッド的な時空間とは何なのかは省略する。ドストエフスキーの世界での「叙述の特異な遠近法」に関してはこの劇評を書くために応用できるかと思って参考文献にしてみたら既成のぼんやりしたバフチン理解が粉砕された山城むつみの「ドストエフスキー」に当たってください。500ページ以上に渡って「自分の心の奥底に秘めた言葉が他人の口から発せられたときに生じる斥力」を凝視した現代演劇人必読の書である。
『では、自分自身の内部の言葉と全く同じ言葉であるにもかかわらず、それが他者の口を経て外部から送り返されて来ると、なぜかくも強い斥力が生じるのか。
イワンの反撥は、精神分析治療における患者の「抵抗」を連想させる。この類推において、イワンが憎悪と反撥を超えてアリョーシャの言葉に同意すれば、イワンは烈しい動揺の中で自分自身の言葉を支えることができるとは、分析医の洞察した言葉を患者が「抵抗」の果てに認知したときに治癒が生じるという事態に対応している。心の深層に大洋のように広がる無意識の領域とはイメージを喚起するための比喩にすぎない。無意識とは、端的には、自分自身の言葉を自分ではとらまえることができないということにほかならない。それは、いいかえれば、自分自身では知り得ないが、他者を経由してなら知り得るということでもある。人は自分自身の言葉を、他者の口から発せられたそれを受け入れるという回路でしか認識しえない。人間のすべての悲劇はそこから発しているのではないか。イワンが自分を説得しようと語った言葉をアリョーシャが投げ返してくるとき、その言葉はもとの自分自身の言葉と意味も形式も同一ながら、イワンにとって全く別のものとなってしまっている。両者の間には差異がある。ならば、無意識とは、他者を経由した一つの言葉に生じるその差異、そのずれのことだと言ってもいいだろう。自身に対して発する内的な言葉(「俺じゃない」)をイワンはよく知っているつもりだが、しかしその内的な言葉を自分に発するまさにそのことで彼は何かを抑圧している。何が抑圧されているのか、それはイワンには知り得ない。ただし、アリョーシャがイワンのその内的言葉を見透して、それを知己の言葉として彼に投げ返すとき、言葉とともに、抑圧されたものもイワンに回帰してゆく。してみれば、無意識とは、自分自身の言葉が他者を経由して戻って来るときに付着しているこの何ものかのことなのか。それが回帰して来たとき、イワンは「不気味な」気持ちになる。強い「抵抗」を覚える。だが、その抵抗を克服して受け容れることができれば、そのときに治癒が生じるのだろう。ドストエフスキーは繰り返し精神分析的に読まれてきたが、この作家において問題となる無意識は、たとえば父親殺しの欲望(エディプス・コンプレックス)といったわかりやすいところにはない。「あなたじゃない」というこの小さな言葉に付着してイワンとアリョーシャの間を循環しているものが無意識なのだ。ドストエフスキーを読み解くために、心に染み透る言葉と、それをめぐって生じる斥力を対話の言葉の問題として探究しているとき、バフチンはその意味での無意識を分析していると言っていい。バフチン自身はフロイト主義に批判的だったが、彼のドストエフスキー読解はフロイトの臨床理論と構造的に合致しているのである。』(山城むつみ「ドストエフスキー」)
よく考えたら「それが在ったところに自我を在らしめよ」の教えに凝縮されているように、フロイト~ラカンの精神分析には「言っていることとやっていることのズレ」の図式が満ち満ちているのだった。
『「難解さ」の「誤解の幅」において解釈や意味の厚みが出現し、それが人間の言語や生について欠くべからざる要素となるという「難解の擁護」という思考』だとその性質を明確化している佐々木中が「夜戦と永遠」で『彼はシュレーゲルとマラルメを継ぐ、アイロニカルな難解さの擁護者のひとりなのだ。』と指摘しているように、数学素の濫発をもってして悪名高いジャック・ラカンの「性別化の論理式」はこうである。『男性の側には、例外者(∃x¬(Φx))が普遍(∀xΦx)を構成するという構造を、女性の側には、普遍を決定する例外がなく(¬(∃x)¬(Φx))、象徴的決定に対して過剰となる(¬(∀x)Φx)という構造を置いている。』といったこの式の読み方は十川幸司「精神分析への抵抗」の第七章などで頑張ってください。
男性:∀xΦx,∃x¬(Φx)
女性:¬(∀x)Φx,¬(∃x)¬(Φx)
だからといってこういった込み入ったミステリアスな図式を戯曲に取り入れてそのまま台詞の中で発音させてしまう劇団など実在するわけが……あ!それがリクウズルームなのだった。
山下望
映画美学校批評家養成ギブス卒。2008年より現代音楽・映画・美術・演劇・アニメ・アイドル・ダンス・ヒップホップ……etc.を論じる独立系批評誌「アラザル」の編集・執筆に携わり、現在VOL.9まで刊行。(https://arazaru.stores.jp/)
Twitter ID:@yamemashitaa