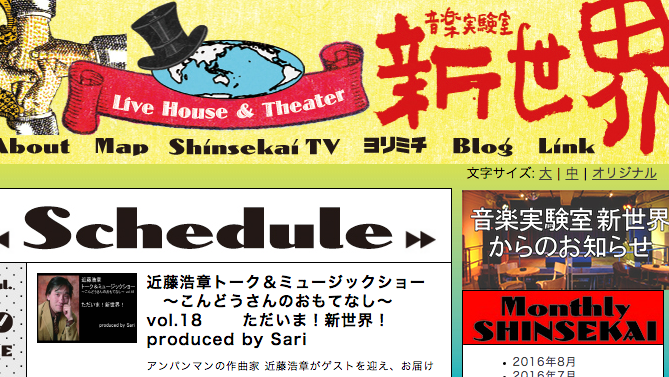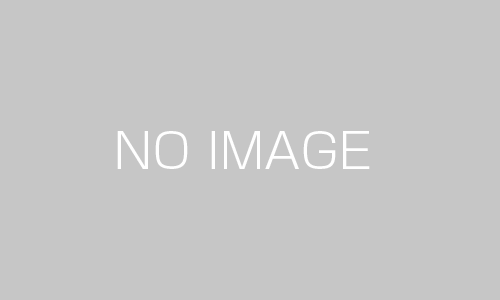……お茶を濁すような形になってしまったが、まだ話は終わっていないので気を取り直して先に進むとここまでリクウズルームの世界を跡付けてきた結果、「内面」から切り離された俳優の演技を操作・振り付けする現代口語演劇の変形バージョンとして、私はその言語(戯曲)と身体(俳優)の軋み=演劇の実践による、相対主義が突き進んだ現代的思考のパターンとして根が深い「シニシズム」批判の契機が見出せるのではないかと予想しているのだが、舞台上で起きている可笑しなズレの在り様についてここでさらに一旦視点を変えてみよう。
そもそもの「シニカル」の語源であるキュニコス派(犬儒派)まで遡ると、『もとより近代に生きる者は、程度の差こそあれ、シニカルであることから逃れることはできない。』という前提から『シニシズムの完成者であると同時に、それへのオルタナティヴもカントは考えていた。』と解説する文芸批評家の池田雄一がさりげなく触れているように、プリミティヴな演劇性があることがわかる。
『古代ギリシャ時代の犬儒派のひとりであったディオゲネスは、運動は存在しないという有名なエレア派のパラドックス(アキレスと亀など)に対して、みずから立って歩き回ることによって、反証したという。問題の抽象性に対して、身体の具体性で答えたことになる。第一批判におけるカントの理性批判も、それと同じような態度でなされている。(……)したがってキニシズムの使命は、生き方と教えとが分離している、その意味では「偽善」としか言いようのない哲学に対し、みずからの身体でもって「本当のこと」を思い知らせることにある。』(池田雄一「カントの哲学 シニシズムを超えて」より)
言うなれば、ベケットに影響を与えてもいる「甕の中に住んだ」ディオゲネスは「思想=問題の抽象性」と「生き方=身体の具象性」との一致に向かって裸に剥かれた「食い違い」をそのまま上演してしまうのである。 その他、偶々手元にあった「マネからフランシス・ベーコンまで、ボードレールからサミュエル・ベケットやバロウズまで」古代から中世を経て絶え間なく復活する『近代芸術のアンチ・プラトン主義』へと『その闘争の執拗な持続』が見いだされる『真理のスキャンダルのなかにある生の形式としてのキュニコス派』のポジティブな側面を説く、フーコー「真理への勇気」を論じた佐々木中の「この執拗な犬ども」では『プラトンと幾度もユーモラスと言っていい応酬を演じ、果ては彼が人間は二本足の羽根のない動物であると定義すればその教室に羽を毟った鶏を投げ込んでこれが人間なのだなと嗤った。』という言動が記録されている。佐々木透の作品を解読するためにこの文章を書き始めているわけなのだが、佐々木中のこの『プラトン主義は、この世界の背後あるいは上に「真の世界」を前提とする。(……)そこで問題になるのは端的に「この世界とは別の生」「他界」における「永生」である。しかしキュニコス派において問題になるのは「他界の問題ではない。別の生の問題である」。つまり「この世界における別の生」が問題となるのであり、そしてその別の生こそが彼らにとって真の生なのだ。』という主張を噛み砕くにはさっきの佐々木敦の「到達不可能な理想型は実はない」の議論にまで一旦戻ってください。
で、このキュニコス派の『公式的な文化、権威となった思想、あるいは人物などに対する挑発の精神、それらの偽善を暴きたてる不遜の魂』(カントの哲学)が20世紀になって「ファシズムの土壌になったシニシズム」にどうやって移行していったのかは「方法としての演技―ニーチェの唯物論」という著作もあるペーター・スローターダイクの「シニカル理性批判」で追及されているそうだ……。そこでスローターダイクが主張しているのは、「理論」たりえないシニシズム的態度は「理念と現実とのギャップを暴露するパフォーマンス」だということである。
そして『キニカルな挑発、暴露に対する、支配者側の応答の態度としてシニシズムがある。(……)そしてこれは重要なことだが、キニシズムがひとつの態度であって理論ではない以上、キニカルな人間はこの支配者側からの応答に答えるすべを持たない。こうなると前者に対しては、それの滑稽さを冷笑する態度、後者に対しては、そんなこと自分で考えろ(支配者側なんだから)という子供じみた居直りしか示せないはずである』。この真実が暴露された後の挑発側と支配者側の居直り的態度の連鎖が「キニシズム(批判)のシニシズムへの転落」である。
『キニシズムは、先に述べたように、ひとつの理論たりえず、また「独自の」理論を持つこともできない。認知上のキニシズムとは、知との付き合い方のひとつ、知を相対化し皮肉る、応用し止揚する一形態にほかならない。それは、理論やイデオロギーが自分に仕掛けてきたものに対する、生きんとする意志の側からの回答なのだ。精神的な生存術にして知的なレジスタンス、風刺にして「批判」である。〔「シニカル理性批判」、二九四頁〕
キニシズム、あるいは批判とは、ひとつの「態度」であって「理論」ではない。それらは「実証的な」理論の提示する誤った法則や、それによる暴力から身をまもるための実践的な身振りである。スローターダイクは、そのような態度の例として、マルクス主義やニーチェの哲学、あるいは精神分析などをあげている。それらの運動や批判などで展開されている言説は、態度であって理論ではない。したがって、それらを無理に理論として実定化し体系化することによって、俗流マルクス主義やニーチェ主義、胡散くさい疑似精神分析などが登場することになるだろう。』(池田雄一「カントの哲学」)
ここまで来ると、無理に理論化・体系化することができないシニカルなシアトリカルさとして後の「パフォーマティヴで散種的なテキスト読解」(東浩紀)としてのジャック・デリダの「脱構築」にまで連なる「批判主義」の運動が貫通してしまった。
例えば「劇場型」犯罪という慣用句で使われてもいる演劇性(シアトリカリティ)とはつまり、美学/ダンス研究者の木村覚が『観客の(A)「見る」欲望と表現する者の(D)「見せる」欲望とが見事両方成就する時、両者の内に幸福な関係が結ばれると考えていいでしょう。』と整理しているように、人前で何かを「見せる」という行為(正確には受動的に見られる/見せられるではなく見せる/見るという規約的な共犯関係)には、即物的なマテリアルの表面とは別に不可避的にイリュージョン=フィクションの層が覆い被さってこざるをえない。
『(……)人間は、どこまでも演劇的な状況から逃れることは出来ないのです。例えば、言語というきわめて人間的な道具を、人間は学ぶあるいは真似ぶことによって手にします。母や父の声真似をする、その声真似がいつの間にか自分の言葉と思い込めるようになっていきます。そうして自分の言葉が生まれるとしても、他人から、あるいは自分の住む共同体から借りてきた道具を用いてコミュニケーションしているという事実は、常に隠しようがなく残存しているはずです。その表現は自分だけのものではない、その表現する者と表現の手段とのズレを忘れたくて、隠し通そうとして、人間はさりげなさを求めているのかもしれません。
けれども、ひとの振る舞いというのは、どこまでも演劇性を露呈することになるわざとらしさから逃れることが出来ないものなのです。人間が集い、何かしらの出来事が発生する時、見る者という立場、見られる者という立場、そうした二つの役割から降りて中立的な存在でいることは、そう簡単なことではないのです。』(木村覚「未来のダンスを開発する フィジカル・アート・セオリー入門」より)
元々その「演劇性」の概念が広まったきっかけのアメリカの評論家のマイケル・フリードが自律した物体ではなく「物体らしさ Objecthood」だとミニマリズムの美術を批判したような、それらしき空間の配置さえあれば見られる物体は何でもよくなる逆説。『さらに、彫刻家トニー・スミスが深夜に建設中の高速道路で得たという経験談に、状況の設置が整えば、客体としての芸術作品がなくとも、その代理物が自動的に充填されてしまうというシアトリカリティの逆説を観ている。「作品自体はますます不必要になるということである」(「芸術と客体性」)』(岡崎乾二郎「ルネサンス 経験の条件」より)。
一見遠いようだけどこの「らしさ」によるシアトリカリティ批判は、「炎上」する条件さえ揃えばインターネット上のSNSや掲示板を徘徊する暇を持て余した匿名集団が実名の有名人(時には個人情報が無防備な一般人)を標的にして共犯的な「問題提起」によって参加している当人にとっては暴露されるスキャンダルの「内容」がどうでもよくても燃え続ける(ネガティヴな注目が集まり続ける)ことで実際は「見て見ぬふりをする」制度の延命に加担するネット空間の現象にも置き換えられる。かつて中平卓馬が「なぜ、植物図鑑か」で問い糺していたように、そこではスペクタクルを「見る欲望」がどんなフレームによって可能になっているのかだけは疑われていない……。
このネット上の「炎上」騒動、言い換えるとスペクタクル化した「梯子外し」で使われるのが、祭り上げられる本人が発信した情報のみを頼りに画像やブログの過去の履歴が社会的信用を裏切る方向で『記号が孕む「内的な差異」が「別の何か」を永遠に名指し続けてしまう言語=テクストの「宿命」』を倫理の問題にした(土田友則)、にも関わらず人文・社会科学陣営の中で毀誉褒貶に晒されつつ時にそのメソッドが悪用されもするポール・ド・マン的にアレゴリカルに読み替えられるという「脱構築派」の手法なのである。
おまけにそれに関して突然思い出したのが、1963年の大島渚監督のTVドキュメンタリー『忘れられた皇軍』である。2014年1月14日の深夜に『反骨のドキュメンタリスト 大島渚「忘れられた皇軍」という衝撃』と題された番組の中で日本テレビに残っていた50年前の映像を再検証するという形で全編が放映された。
実際に観てみると、被害者/加害者という図式による四角四面な「怒り」の訴えばかりがフィーチャーされて語られがちな『忘れられた皇軍』ですが、劇伴として選択されたアート・ブレイキーのジャズドラムが主人公の傷痍軍人達が白装束で固めた行進の場面以降もずっと鳴っているという演出(時折り彼らの軍歌の合唱とミックスされる)からして、日本政府からも韓国政府からも見放された悲惨な境遇にある彼ら元軍人の路上で公衆を惹きつけて命懸けで道化的に口上を述べる、ストリートで培われたセルフ見世物小屋(サーカス団)的ともいえる「演技」力にこそ注目したい。(キュニコス派のパレーシアにも通じる?)
「本当の私の痛み」を自身の声で語るためには、人前で上手く聴き手を抑揚(リズム)に乗せて演じなくてはならない。つまり意外にもヒップホップだった。人目を惹くために旗を立てる、決まり文句で韻を踏むなど、現代演劇およびヒップホップにも通じるそのパフォーマンスの虚実の多層さ(制作当時の終戦から18年後の時点で既に「見放された兵隊たち」に無関心になっている日本人に対する抗議でそうせざるをえない政治的手段の次元)をどう受け取ることができるのかという視点こそ、ネトウヨ的なナイーブに「正しい=マスメディアに隠された純潔な現実(歴史)」を追い求める心性につけいられることのない、これが撮られた当時から50年後の現在だからできる、目に見える身体的欠損を反体制の疎外論的シンボルにしているこのドキュメンタリーの見方だと思う。フーコーが翻訳される以前の権力観っていうか。これでいいのだろうか、と視聴者を挑発するほぼ大島渚のアジテーションと化したナレーションといい、大島が捉える傷遺軍人会は「ありのままの真実」というよりは「社会の矛盾と闘うための物語」をシャウトするラッパーのプロモーションビデオとして再評価できる。
すなわち告発文書としてメッセージのみを読み取るか、映像表現として見る(+聴く)ことを学ぶか、っていう違いである。
その最大の争点であるラストショットではサングラスを外してカメラを見つめ返す「盲目」のクローズアップが別の異様な何かのように見えてくる、つまりカメラが対面する視線の「盲目」が反転する。この日本人と在日軍人の視線の非対称性というのは四方田犬彦「大島渚と日本」での批評を参照してください。
しかし2014年の番組の作りとしては、日本テレビの倉庫からフィルムを発掘して紹介するだけで偉業だと思いますが、『忘れられた皇軍』を中心にして関係者(スタッフや監督の妻・小山明子)に取材するドキュメンタリーとしては、この軍人会の保障問題が未だ解決していないという事情によるものだとしても、当時のメッセージ(反権力の戦略)をそのままなぞっている(最後に映像を模倣して両目のアップになる)のは疑問があった。戦争による目に見える身体的欠損VS.その代償としての国家の保障という図式だとその反動でネトウヨが生まれ、みたいなシーソーゲームの繰り返しだし、終戦から18年後からさらに50年後という現在の状況では戦争が無い状態の方が長いのでカメラにわかりやすく写らない見えない問題はどうするのかと考えざるをえないということである。
どんなイメージを付け加えればよかったかのかといえば、彼らを電車の中や路上で眺める傍観者・視聴者の反復をこそ捉えるべきだったのではないか、とここまで考えさせられてしまった時点でクリティカルな映像を内包している企画だった。
『だがさらに驚くべきは、その失明した両眼から涙が流れ落ちていることだ。かつてジャック・デリダが「盲者の記憶」(みすず書房、一九九八)のなかで、眼のもっとも重要な役割とは見ることではなく、涙を流すことであると説いたことを、ここで想起すべきだろうか。「忘れられた皇軍」はこうして単なる隠蔽された歴史の告発に留まろうとせず、映画における見るという行為に、ある本源的な問いを突きつけているのである。』(四方田犬彦「大島渚と日本」より)
ここでBGM:考えれば 考えるほど わかんない 細かいこと ばっかりで 縛ったりせずに オーイェー!(オーイェー!)
考えても 考えてもね 答えは出ないけど おそらく 愛してる 君のこと 地球は愛の力で グルグル 回ってる……(lyrical school「PARADE」より)
以上、「真実を暴露するパフォーマンス」としてのシニカル/シアトリカルの桎梏を追ってきて、どうしても避けては通れないのが判明したので寄り道しますが、「ウソだとわかっちゃいることと、それに拘るのをやめられないシニシズム(アイロニー)」が主題と演出手法の両方に跨った舞台上での「言っていることとやっていることのズレ」の提示と通じているのではないかと考えるきっかけとなったある作品の「なぜ夫はコロッケにマヨネーズ以外で味付けすると激怒するのか問題」をまだどこにも書いていなかったのでついでにレビューしてしまおう。
というのは同じくアゴラ劇場で 2013年8月19日に観た水素74%の『謎の球体X』(作・演出:田川啓介)である。コロッケに醤油で味を付けると激怒するが、なぜマヨネーズなら不味くないのか。劇中で展開する人間関係は、このような非常に自己中心的に偏った「好き嫌い」の問題に規定されている。
一軒家の縁側と卓袱台とキャビネット型の収納以外が白く捨象されたセットで、そこで暮らしている「人に頼まれると断れない性格のため体に包帯が絶えない妻」+「街中でキチガイと噂されるDVの疑いがある夫」を主軸に据えて、「俺は君を守るために生まれてきたんだ!」→「あたしの味方はあなただけ」→「もう信用できないから他人だ、出てけ」「じゃあ何のために生きてるの?」「知らないよ、そんなの自分で考えな」(以下ループ)というように、 理不尽だとしか思えない「私」的な物差しでそれぞれ互いに敵/味方かどうかの境界線を気にしつづけて執拗に脅える思考が必然的におちいる、疑心暗鬼的な依存/支配関係のシーソーゲームが、「災害で出身地の街が壊れたためにその家に侵入してくる、父親に世界で一番可愛いと溺愛されて育てられた妻の妹」+「突然何かの力によって今生まれてきたばかりで何のために生まれてきたのかわからないと訴える通りすがりの男」、「夫婦が住む家の大家で家賃を取り立てに来るお節介で心配性の女+その旦那で物心ついた時からずっと不治の病を介護されてきた男」、を加えた3組のカップルの言動に連鎖してひっくり返り続ける。
巧妙にリアリティを抽出した(とりわけ、冒頭で妻を訪ねて中学以来に借金をせびりに来た水商売風の女との「言わせないでよ( 手を差しのべて)」「え?」というやり取りが絶妙に気不味い「二千円しか持ってない」財布をめぐるあの攻防……)、現代メロドラマの巨匠ことファスビンダーの映画を思わせる貧しくペラペラな方向に寓話化された登場人物達は全員揃いも揃って空回りして傷つけ合っているのだが、そして「久しぶりに再会できた中学の同級生なんだから」「夫婦だから」「家族だから」「運命的に出会ったから」自分のために他人が何かしてくれるという、傍から見ればよくわからない論理の、言うなれば先ほどから引用し続けている池田雄一が『カントの哲学』で現代版に再解釈している「ロマン主義的で機会原因論的なシニシズム」にアディクトしているように思える。
つまりどういうことかというと、そこで分析される概念を順番に説明すると、カント哲学に原型を遡ることができる現代的シニシズムとは、何らかの理念的に大事な○○(ここでは例えば「家族の絆」「真実の愛」)がウソだとわかっちゃいることと、それにすがるのをやめられないことが表裏一体になった状態である。
そして日本の状況に置き換えたバージョンの『シニカルな主体が選択する認識・行動の原理としての機会原因論的シニシズム』は、オウム真理教事件や「幸福な薬物依存者」にも似た「動物化」したオタク文化、ネット上のコミュニケーションを具体例にして取り出されるのだが、池田雄一の解釈では、ドイツの法学者カール・シュミットの「政治におけるロマン主義的な態度への批判」 から援用される機会原因論的行動原理とは、恩寵のように受動的にもたらされる身体的快/不快=「趣味」に関わっている。さらに、この「趣味」は初期における資本主義の発展とともに拡張されて使われるようになった「味覚の隠喩」が語源にあると指摘されている。
『このような趣味概念は、身体として語られる場合、個々の判断にかんして極端に個人主義的な態度を要求する。それは身体的な反応にもとづいているのだから、他人と議論する余地はない。他人の趣味に口を挟むのは、プライベートの侵害である、という発想だ。そして一方でそれが精神性や超越性として語られる場合、その判断については普遍的な同意を要求する。(……)趣味それ自身が天からの授かり物のようなものなのだから、議論する余地のない全面的な同意のみが求められるだろう。したがって趣味の反対語は悪趣味ではなくて、無趣味つまり野暮ということになる。いい趣味と悪い趣味があるのではなくて、趣味があるのかないのかが問われるのだ。したがって趣味という概念には、それをめぐって他人と議論する場、政治的な領域が存在しないということになる。人は、他人の趣味については、自動化された同意の身ぶりをしめすか、端的に無関心を装うか、いずれかの態度のみを要求されることになる。/(……)したがって、機会原因論的シニシズムとは、資本制によって細分化された趣味のイデオロギー、という形態をとることになる。』(「カントの哲学 シニシズムを超えて」より)
劇中の一場面にあるように、夫の健児にとっては、「なんでソースが切れているんだ!」と激怒して家の外が嵐だろうが関係なく高圧的に今すぐ妻に買いに走らせるほどコロッケに醤油をかけて食べるのは断じて許せないが、実はマヨネーズだったらありだったというのは徹底して「趣味」=独特のセンスの強制である。
つまり言い換えると、好きか嫌いかの(「神の恩寵」としての)美的趣味判断で世界を覆い尽くそうとする態度の帰結として、偶発的な「気持ちが良い」出来事をきっかけにして○○に入るのは国家でも民族でも、もしくは恋人でも家族でもアイドルでも良くて、他人にとっては些細なきっかけでコロコロ変わるように見えるのだが、そこで発動するのが(細かい因果関係は超越した「真の原因」としての)、○○のために生まれてきたんだ!→○○以外は無意味な見せかけのゴミなので○○のために死ねる、となって現実が仮象の偽物に反転する(「地球」が「謎の球体X」へと変貌する?)原理である。
『趣味の事柄に関して裁判官の役目を果すためには、我々は事物の実在にいささかたりとも心を奪われてはならない、要するにこの点に関しては、飽くまで無関心でなければならないのである』……。(カント「判断力批判」より)
この彼・彼女ら自身の身体的反応を普遍化する「自分にとっての気持ち良さ」に没入した状態こそ、それを頭の中から開いてそれぞれ別の肉体を持った俳優が実演する舞台に乗せると、各人物の脳内から漏れた「都合の良さ」が食いちがって衝突するこの上なく気持ち悪い世界観になる。ゆえに彼・彼女らの聞く耳を持たない話の噛み合わなさは、台詞の会話から聞こえる「都合の良いことばっか言ってんじゃねえ」「適当なこと言ってんじゃねえ」というように他人の言動が嘘臭い、希薄なものにしか感じられなくなっている理由は、ここにある。
ちなみに不可能だとわかっている失われた真正な絆(赤い糸?)を回復しようとするのがロマン主義の思想であった。
『原因と結果の経験論的かつ機械論的な連鎖に主体が組み込まれることへの拒否、ロマン主義にはそのような態度が前提となっている。(……)太陽がまぶしすぎたから、通りがかりの通行人にダイブした。月があまりにもきれいだったから、家に帰って寝た。世のなか楽しすぎるから、みんなで練炭自殺。これらの行動は、明確な因果関係にもとづくものではない。というより因果関係を主体があえて切断している。この「あえて」がロマン派的心性にとって重要だということになる。
そのようにみていくと、機会原因論的な認識あるいは行動というのは、おなじくロマン派的な「イロニー」と似た構造をもつということになる。ロマン的イロニーとは何か。主体がどうでもいいような些末な事柄にあえてこだわってみせることによって、世界全体を「大いなる仮象」として美的に解釈する態度のことだ。シュミットのいう機会原因論は、このような態度に限りなく近いものと思われる。シュミット的な機会原因論による認識とは、世界それ自身を、美的なもの、つまり自由という理念つまり否定性そのものに憑依した仮象だと仮定することによって成立しているのだ。』(同書)
この舞台で俎上に乗せられた夫婦の関係が、友情なり愛情なりの真実の絆が、困った時の人助けが「ウソだとわかっちゃいるけどやめられない」について視点を変えると、再演に当たっての山崎健太によるインタビューで作・演出の田川啓介は、『初演では登場人物の一人がこの世界は全部ウソ、つまり芝居だって気づくところがあったんですけど、今回はそういうメタな仕掛けはなくなっています。そもそも初演のときにメタ視点を盛り込んだのは自分の世界から外に出たいって気持ちがあったからなんです。戯曲って全部自分が書いた世界だから、そこには自分の中から出てきたものしかないし、全部自分がコントロールできるものでしかない。でも実際の世界は自分の思い通りになんかいかないじゃないですか。その差みたいなのが気持ち悪かったから、戯曲、つまり自分の世界を外側に開くつもりでメタな視点を取り入れたんです。でも結局それも自分から出てきたものだし、人から評価されたのはメタな構成じゃなくてむしろ「自分」が強く出てる部分だった。だからそれからは外側に行くよりもむしろ「自分」を掘り下げる方向で書くようになったんです。』と初演からの変更点を語っている。
中学の時に飛び降りたことがある妻に対する「大丈夫、だなんてあなたの嘘は信じないから、安心して」。不治の病を抱えた男への「あたしが辛くなるからもっと可哀想にしてよ!」「助けてくれるのはいいけど、優越感が見えないようにしてくれ」……等々の、他人の気持ちがわからないと泣き叫ぶにも程がある、逆ギレ的に一方通行に押し付けられるひねくれた台詞の数々で訴えられるのは、「自己保身のための同情」と「ナルシスティックな罪悪感の発露」がいかに奇怪なものかがフォーカスされ、 けどその度に爆笑・失笑が起きていたのがポイントだろう。家族を思いやるようでいて実は……な挿話は自伝寄りだけどハイバイの『て』もそうだった。
台風で家が壊れようが、刃物が振り回されようが、介護に疲れた家族に見捨てられかけようが、互いに「こいつはどうしようもない→こいつは……しょうがない」という一種の奇妙な均衡が垣間見えるのはささやかなユーモアだといえるだろう。つまり、よくよく振り返るとこの作品には絶対的な加害者としての悪役が存在しない、弱者が足を引っ張りあう世界だったという点ではメロドラマ的である。互いに理解不可能なバケモノ!と罵り合う、鏡に写したように反復して交錯する殺意によって刃物が振り回されても結局誰も刺されず(演じられているのは物理的な暴力ではなく)、血が一滴も流れないのにアウトレイジな舞台だった。
山下望
映画美学校批評家養成ギブス卒。2008年より現代音楽・映画・美術・演劇・アニメ・アイドル・ダンス・ヒップホップ……etc.を論じる独立系批評誌「アラザル」の編集・執筆に携わり、現在VOL.9まで刊行。(https://arazaru.stores.jp/)
Twitter ID:@yamemashitaa