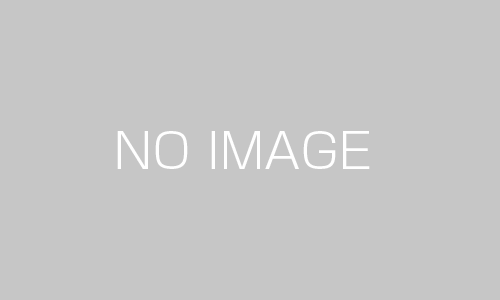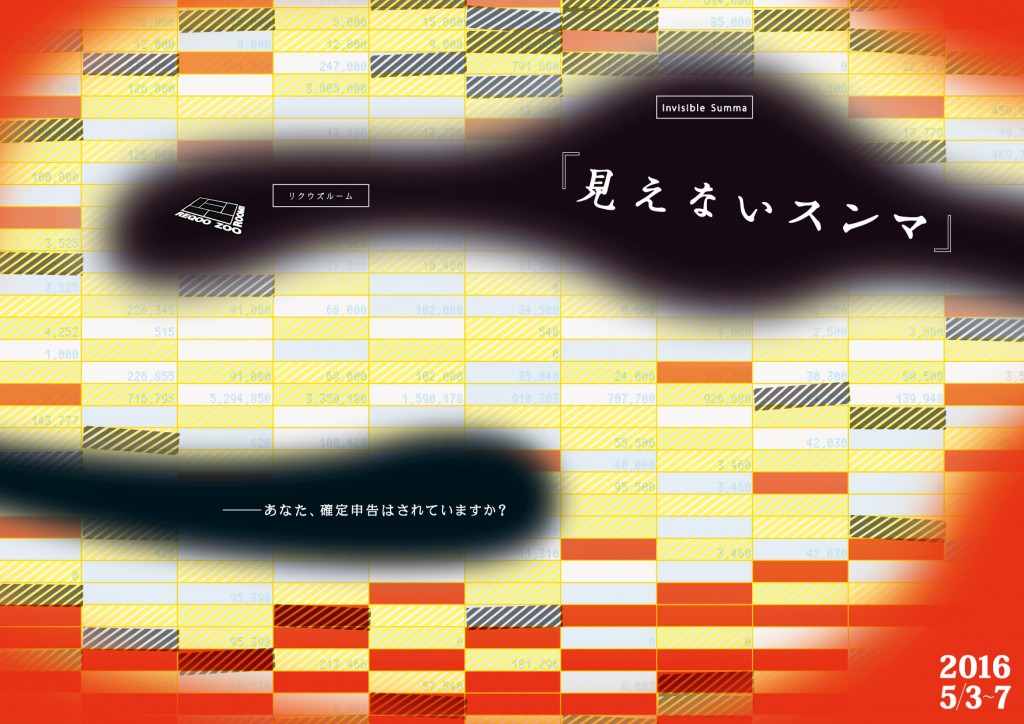このようにして、水素74%の『謎の球体X』はカントが分析したような個人的・主観的な「趣味判断」の機械的に従うしかない強制力(経験的利害を離れた対象に「無関心」な、「目的なき合目的性」の判断なので)をグロテスクなまでに誇張&アレンジし、それがいかに「自分の味方しかいない世界」を作り出そうとするかのメカニズムを寓話的に抉り出してみせた。そこで描かれる「シニカルな現代人」が抱える不気味さの中でも、とりわけわが身を振り返っても身につまされるのが、「趣味」がもたらす身体の徹底した受動性が精神的でも物質的でもない「真の原因としての<神>の意志」に動かされるあやつり人形に反転する、というモチーフである。
『真の原因である神によって、まさに神経つきの紐でつるされた操り人形。古典的な機会原因論によってイメージできるのは、そのような人間像である。神の経糸。機会原因論とは、神経という言葉それ自身がアレゴリカルにしめしている状況だと考えることができる。』(同書)
そこで掘り下げられている、時代的にはデカルトの後のスピノザと同世代でヒュームの因果論の元にもなった17世紀の哲学者・マルブランシュについては、木田直人の解説によれば、機会原因論の特徴は、「被造物の無力化」である。そして木田直人を参照する仲正昌樹は結果を原因(真の原因=神の意志が発現するきっかけ)と取り違える機会主義は近代のロマン主義的思考に継承された、と「無限の反省」を通して合理的な自我をアイロニカルに相対化し続けるロマン派の批評スタイルがカトリック保守主義の秩序に則った「決断主義」によってディスられている書物のシュミット「政治的ロマン主義」の講義で言っている。
『実際、マルブランシュは、被造世界のあらゆる局面から力能を剥奪する。第一の局面は、物体間の秩序である。たとえば、ビリヤードで白い玉が赤い玉に衝突する場合、白い玉をもって赤い玉の運動という結果の原因と見なすことは、われわれの日常的理解としては何ら問題ないであろう。だが、マルブランシュはここに疑義を呈するのである。なぜなら、物体とは延長にほかならないのだから、他の物体を動かす力能はないはずである。そこで、彼は赤い玉の運動の真の原因は、神が制定した運動の法則であり、白い玉の衝突は、この法則を現実化させる機会原因にすぎないと主張する。ここに被造世界の無力化のプロトタイプを彼はみいだすのである。
この物体間の因果のイメージを、マルブランシュは心身問題にも適用する。(……)マルブランシュの意図とは裏腹に、神を骨抜きにした因果論が十八世紀を彩ることになるだろう。すなわちこの機会原因論こそ、ヒュームの因果論の立役者なのであり、ひいては、コント(一七九八‐一八五七)の実証主義の源流なのである。』(木田直人「ものはなぜ見えるのか マルブランシュの自然的判断理論」)
『この世界の運動の全ては、神によって起動されていて、個々の人間や物体は、その運動の「きっかけ」に遇々なったにすぎないわけです。
そうなってくると、私が何かやっているように見えても、実際には、神が私の手足を使ってやっていることであって、私は単なる観客にすぎない、という感じになる。
(……)日本語にも、「筆が進む」という言い方がありますね。私自身の意志とは関わりなく、“私”の中、あるいは、“私”の背後にある“何か”がペンを動かしているような言い方ですね。ロマン派の文学作品には、そのこと自体をテーマ化しているもの、つまり、「私」に書かせている「目に見えぬ力」を登場人物自身が意識し、そこから新たに物語が展開するというようなモチーフがしばしば見受けられます。』(仲正昌樹「カール・シュミット入門講義」より)
ところで哲学者のマルブランシュは同じく「機会原因論」を提唱したゲーリンクスと共にサミュエル・ベケットの戯曲にも登場するのだという奇遇な豆知識……。
『自分の意思をもってしては何事もなし得ない人間は、神の摂理を謙虚に受け入れることが課題になる。これこそベケットが『マーフィー』にラテン語で引用した「わたしが何もできないところでは何も意志すべきではない」というゲーリンクスのものとされる言葉である。
マルブランシュはさらに精神と身体との関係だけでなく、物体が物体に衝突するように見える現象も実は神の働きの機会原因によるものとし、すべての自然現象を神の意思によるものとした。『事の次第』に「薔薇色あせたマルブランシュ」という言葉があるが「わたしたち二人」について歩き出す犬(デカルトやマルブランシュは物体とみなした)も「わたしたち二人と無関係に犬は同時に同じ観念を抱いただけ」と機会原因論解説がのぞく。』(森尚也、「ベケット大全」より)
劇場空間、観客、俳優の脳ばかりか身体までをもかどかわすリクウズルームの言語の回転に通りすがりの様々なる批評の言葉が巻き込まれるとどうなるかというと今こうなっているわけだが、1956年のドン・シーゲル監督の『ボディ・スナッチャー/恐怖の街』から始まって2007年までになぜ全部合わせて4回も繰り返し映画化されるのか、その物語がアメリカ人の深層にとり憑く理由を分析している時間がないのが残念だ。
おそらく、住民達が脅える「無傷な別人」達の指紋のツルツルさの同質性が象徴する、すなわち野球やコンビニやファミレスを題材にしたチェルフィッチュ(岡田利規)の諸作へも流れ込んでいる幸福な消費生活の同調圧力がキーワードである。さっきからその輪郭を浮かび上がらせようとしている、商品の交換体系によって世界が覆い尽くされていく資本主義社会での些末な「趣味判断」のイデオロギー、受動的な「神の操り人形」としての機会原因論的にシニカルな、「わかっちゃいるけど止められない」身体は、チェルフィッチュの舞台の至る所でも蠢いている。きりがないので詳しく引用するのは控えるが、マルブランシュの機会原因論の消費社会バージョン、売れたという事実がそのままモード=命令になる、いじめられたという事実(結果)がそのまま原因にすり替わる問題は池田雄一が「カントの哲学」の次に「メガ・クリティック」で叙述している。『このように結果と原因をすり替えるという所作は、自己責任論と呼ばれる言説をつくりだす。たとえば経済的な弱者に対して「彼らが貧乏なのは彼ら自身に問題がある」というものである』。そうすると「機会原因論」は一種の「運命論」に近いのだろうか?
改めて岡田利規の場合の「言っていることとやっていることのズレ」を振り返ってみると、言葉(虚構のテキスト)がしぐさを規定するのではなく、言葉としぐさが生まれてくるイメージ(豊かなシニフィエ)を観客にコンセプションする、という方法論が「遡行 変形していくための演劇論」で語られているのだが、最初から紛らわしい表現を使っていたのを遡って今気がついたが、そこでは主題上の「理念と現実のギャップ」の実存的な文学性(アイロニー)とはまた別に、演出手法のレベルで「日常の身体の過剰さ」をミクロな視点で捉え直している。
『このノイズほど、僕にとって身体のおもしろさであり豊かさだと思えるものはありません。しかし演劇において虚構の身体をしつらえていく過程は、たいていの場合、ノイズが切り落とされていく過程ともなっています。剪定される身体。その際にノイズが切り落とされること。それが僕には、とんでもなく取り返しのつかないもったいないことに思えるのです。(……)演劇の身体はそれなりに過剰でなければならないことになっています(と、少なくとも僕は思わされていますし、僕はそれに対して、しかし異論はありません)。そして僕は、日常における身体は、演劇の身体として見てもじゅうぶんに通用するだけの過剰さをすでに備えていると思っています。なぜならそれはとてもスリリングで、かつノイジーだからです。
でも一般には日常の身体のままでは演劇に必要な過剰さを持たないと思われています。でもそれは、日常の身体が何かツルンとしたもので、そこにはスリルもノイズもないと思われているからではないかと僕は思います。または、そうした身体が演劇の身体として提示される場合でも(あるいはそういった提示のほうが)、出来映えの良いものと思われるからではないかと、僕は思っています。
しかし、日常の身体は過剰なのです。少しだけ大袈裟に言うなら、それはいつも混乱しているし、迷走しています。だって生きるのって大変じゃないですか。』(岡田利規「演劇/演技の、ズレている/ズレてない、について」)
岡田が演劇で提示しようとしている、「スリリングで、かつノイジー」で「混乱し、迷走している」日常の身体の過剰さには、ここまで追いかけてきた、近世から現代になってより過酷に市場の見えざる手に揉まれて踊らされる「神の操り人形」としての軋みが含まれているのではないだろうか。それもまた『自分自身では知り得ないが、他者を経由してなら知り得る』無意識の立てるノイズである。そして言葉(主題)のレベルでも、初期の錯綜し、混濁した台詞から見えてくる、「三月の5日間」での「イラク戦争が始まったので反戦デモを横目にひたすらラブホテルでセックスすることにした」「映画館で会った人にいきなり住所を聞こうとして自爆したので火星に行くしかない」といったようにグダグダに主体性が「無力化」して原因と結果のつながりの糸が縺れて絡まった機会主義的に「こだわりの強い」登場人物達へと形を変えている。このような人物像が半疑問のイントネーションを多用した「キョドリ系」の動きがセットになって演じられるわけだが、正確にはそこからの「自由」を模索しているのが戯曲から読み取れる。
その延長にあるものとして例えば強烈に想起されるのは、2015年の11月に池袋のあうるすぽっとで観た岡田利規・作「God Bless Baseball」のある一場面、ダンサーの捩子ぴじんが扮するイチローをネタにした「野球は人生のアレゴリー」という台詞からの「バットを自分の身体の一部にするのではなく、身体を自分の一部じゃなくする→床面に寝転がった登場人物の4人全員の全身がグニャグニャになった後に脳まで自分のものじゃなくする練習が始まる→その体操がよくできた参加賞が軍のヘリコプター輸送の物資みたいに空から降ってくるイチローの背番号51のゼッケンの布(1959年に最後に加盟したハワイに続く、合衆国に併合された51番目の州の暗示とかかっている)」、劇中で流れる「私を野球に連れてって/僕らのクラブのリーダーは、ミッキーマウスミッキーマウス……強くて明るい元気者」の歌などである。さらにアメリカ人にとって野球場の思い出に結び付いている「やめられない止まらない」というお菓子の広告コピーは日本にも韓国にも各国に共通してあった、というエピソードまで登場するのだが、それを告げるのは途中から俳優達に絡んでくる「神の声」(英語の審判役)なのだった。
ちなみに非言語的な物体も使った(一方で台詞=言葉も異物として放り投げられる)「ディスコミュニケーション」を観客に想像させる演出がなされる「God Bless Baseball」では、まず野球のルールがわからないと言ってバットを振り回していた女子Bに向けて、イチロー役の男が「危ないから傘の下から出るな」という一方通行の言葉とキャッチされないボールを放り投げる振り付けを繰り返した後、舞台上の4人が口を噤んだ静寂の中で観客席の真正面の視界に迫ってくる巨大な丸いものの輪郭が溶け出してボトボト崩れていく出来事を静止して凝視する体験がクライマックスなのだが、途中で野球のボールがホースからの放水に変換されて舞台を囲む垂直の壁が水浸しになる。そしてその光景の直前には、日本人役だけど韓国語で喋る男Aの「父親が好きだった野球」が嫌いになった原因である、9回裏のピンチで打ち上がったセンターフライの球が落下する悪夢の記憶が台詞でモンタージュされていた。
ところでこの作品に出てくる暗示的な主題の細部を変換しようと思えばいくつも「野球を通した日本と韓国とアメリカの関係」の「アレゴリー(寓意)」が読み込めるのだと思われがちだが、しかし観客がスムーズにその変換(翻訳)に成功するのかどうかというと、女子達に野球のルールを理解させようとする流れでおもむろにボールが投げつけられたまま一度も成立しないキャッチボール(言語ゲーム)、登場人物達のエピソードが正しく母語で発語されない日本語と韓国語と英語のミスマッチな組み合わせ(日本人の観客は背景の字幕を読まないと本人の言葉がわからない)、その結果後半にかけて舞台の端に白球が転がって溜まっていく、というひたすら不可逆的に進行する「エラー」が積み重なっていたので観客の知覚にとっては一旦齟齬をきたす断絶の効果が挟まっていたのではないか。宙に放り投げられたボールを受け止めるためのグローブが劇中に登場しないで避けるためだけのボールと傘の組み合わせしかなかったという事実は、その証拠なのか……。
2015年12月17日にゲンロンカフェで催された岡田利規×佐々木敦の対談イベント『ニッポンの演劇#1』でも語られていた、若者の日常を掬い取るリアリズム的な超・口語の戯曲から「現実は一つではない」方向にフィクションの扱いが変わったという話を踏まえると、そもそものフィクションが成立する際の境目で、戯曲の台詞の内容と俳優の身振りが劇中での意味的連関を補完し合いつつ結局すれ違うようなバランスの演出によって、「言っていること(虚構)」が不確定になるように演じる行為が抽象化される、という方法論的な純化がある。
ここまで粘ってようやく、ブレヒトの「異化」を語ることができる。「日本の現代演劇での左翼思想とアングラ演劇に埋もれてしまったブレヒト受容の歪み」を嘆いている、2009年の「エクス・ポ テン/ゼロ」に掲載の岡田利規×宮沢章夫の対談の中では、「現代口語演劇的、つまり自然主義的な考え方は、異化という考え方とは基本的に非常に背反してると思うんです。にも関わらず、現代口語演劇以後の試みの中で異化を再導入しなければならないところがあった」という指摘とか「何も語ることが「ない」のでさえ新しいわけじゃない」とか論点は多彩なのだが、その対談中での語彙を拾うと「異化」と「批評(シニシズム)」は違うんだ、という話が出てきて、まさにこれが「理念と現実のギャップ=真実を暴露するパフォーマンス」をめぐって今までこの劇評で延々と考えたかったことである。で、それが具体的にどう違うのかというと結局解決できなかったのだが、ヒントはいくつもあった。とりあえず、ちょうど手元の事典に「劇場空間が現実認識の学習過程の場になる」っていう簡潔な定義があったのでこれで何とかしてください。
要するに、主題的にも方法論的にも三者三様に異なった形で過剰なノイズが軋んでいるリクウズルーム、水素74%、岡田利規のそれぞれの作品で作動している演劇手法、しばしば倫理道徳的・教条的命法が混じってくる「理念と現実のギャップ」の暴露が「批判」(アイロニーもその一種)で、見慣れた現実を日常の知覚の自動化から分離してモデル化・抽象化するのが「異化」だと整理できる。ここで重要なのは「批判」をやっている中にも「異化」があるっていうことである。同じく演出の/観客の解釈のさじ加減によって異化が批判にも使われる循環構造……。
『「異化」(Verfremdung)は、あることがらを日常馴れ親しんだ連関からずらすことによって、日常感覚とは疎遠な(fremd)もの、見慣れぬものにすることを意味するが、(……)シクロフスキーはヤーコブソンと同様に、芸術と非芸術(日常)とを対立する二つの領域として捉える。日常におけるコミュニケーション言語が、知覚を既存の言語表現に結びつける慣習化、すなわち「自動化」を行うものであるのに対して、芸術言語はその自動化した知覚構造を阻止し日常性を打ち破る。(……)音楽や文字を使用し、心理的演劇法を意図的に拒否した演技法などによって、芝居の流れを中断させ、演じられた場面をあくまでも「演じられたもの」として際立たせる手法が「異化効果」である。日常的にはありきたりの、分かりきった事柄が「異化」によって舞台上で際立たされることによって、観客はそれまで自明であった日常性への反省的視点を獲得する。ブレヒトの「叙事的演劇」は、すでに完成した思考・行動パターンを観客に伝達するのではなく、演じられたシーンをひとつのモデルケースとして提示し、それについての判断を下すよう観客に要求するものである。劇場空間は現実認識の学習過程の場であり、現実変革への行動を導く思考のいわば実験室である。その意味で上からの啓蒙を自負する教条的マルクス主義の政治演劇と対立する。』(大貫敦子、今村仁司=編「現代思想を読む事典」より)
また脱線したけどさておき、その本題の映画の原作であるジャック・フィニイの小説「盗まれた街」でも、舞台となる「他の小都会に較べていくらかさびれてはいるが、といって特に目立つほど変わっているわけでもない」平凡な町・カリフォルニア州サンタ・マイラの住民が寝ているあいだに人知れず細部を吸い取って「本物の人間」と見分けがつかなくなるコピーと入れ替わるのだが、宇宙から飛来してきた寄生生物の「メタモルフォーゼ」のようにしてはたして演劇に批評が動かされているのか批評が演劇を乗っ取って見覚えのない顔へと塗り替えてしまっているのか区別がつかなくなってきたので、そろそろ元の持ち主に返したい。立つ鳥跡を濁さずにきれいに後片付けする間もなく俺は帰らなきゃいけないのでリクウズルームに元の平和な日常が取り戻されたかどうかは神のみぞ知る結末である。
「そうか」とかれは声にさりげない調子をこめようと努めながらいった。「ともかくこれは妄想ではなかったんだ。莢から出てきたものは現実だった。やつらが、生きている人間に化けるんだ。マニーが間違っていたんだ」
「そうだ」
「マイルズ、あの化け物がある人間に完全になりおおせたあとは、真物のほうはどうなるんだろう? 同じ人間が二人できてその辺を歩きまわるのか?」
「それはそうじゃないさ。でなきゃ、ぼくらの目にもつくはずだ。真物がどうなるのか――ぼくにはわからん」
「しかし、それじゃ、どうしてきみの患者たちがそろいもそろってきみのところへやってきて、結局なんでもなかったときみに思わせるような話をしたんだろう。かれらは嘘をついていたんだぜ、マイルズ」(ジャック・フィニイ「盗まれた街」より)
山下望
映画美学校批評家養成ギブス卒。2008年より現代音楽・映画・美術・演劇・アニメ・アイドル・ダンス・ヒップホップ……etc.を論じる独立系批評誌「アラザル」の編集・執筆に携わり、現在VOL.9まで刊行。(https://arazaru.stores.jp/)
Twitter ID:@yamemashitaa